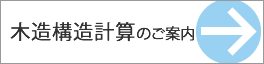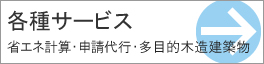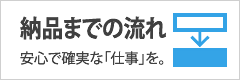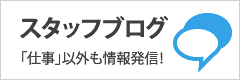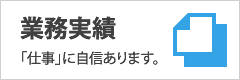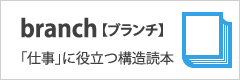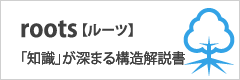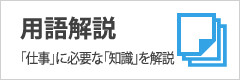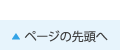前回は令46条第1項について説明しました。
今回は第2項について書きたいと思います。
第2項
「前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。」
これは同条第1項の除外規定となります。
「そうか! 第2項により「壁量検討や耐力壁の釣り合いよく配置(第1項)」の規定が除外されるから耐力壁がなくてもいいんだ!」 という話しではなく、2項を適用するためには逆にハードルが上がると考えたほうがいいかもしれません。
第2項各号の内容を簡単に見ていきましょう。
第1号 次に掲げる基準に適合するもの
(イ)構造上主要な部分である柱および横架材は集成材やJAS材であること(告示第1898号)
告示で樹種により基準強度を定めている。“無等級材”は使用できません。
材料の含水率に対して要求があります。
(ロ)鉄筋コンクリート造の基礎を有し、基礎と土台または直接柱脚が基礎と緊結していること
“一体の鉄筋コンクリート”ではなく、配筋は構造細則に従うRC規準の基礎です。
(ハ)大臣の定める基準に従った構造計算を行うこと(告示第1899号)
第2号 方づえ(その接着する柱が添え木その他これに類するものによって補強されたものに限る)、控え柱または控え壁を有するもので構造耐力上支障がないもの
第2号は木造の簡易な納屋や車庫などで壁(耐力壁)のない建物をイメージしていると考えられます。
しかし、構造的な根拠がない壁や架構を安易に組み入れられるわけではないので、耐震補強の一時的な活用法で設置されたものと解されています。
第1号は、構造材を集成材などして構造計算(許容応力度計算など)で安全を確かめたものは令46条の1項による壁量計算は行わなくてもよいということになります。(告示1100号の検討が除外されることになる。)
しかし、結局のところ構造計算により耐力壁の検討を行うことになります。
「2項適用により、ハードルが上がるならこの2項の規定などいらないのでは・・・」と疑問に思う方もおられるのでは。
確かにごく一般的な木造住宅などでは第2項をわざわざ適用させる必要もないと思います。
では、どういうときにこの2項を適用させるのか・・・
耐力壁の壁倍率という用語を聞いたことがあると思いますが、簡単に表現すると耐力壁の強さを壁倍率という数値で表現しています。
例えば、一般的な筋かい45×90、片筋かいの壁倍率は2.0倍 という感じですね。
この壁倍率の規定は、同条第4項、告示1100号および大臣認定により定められています。
壁倍率を用いて壁量算定をする方法が令46条の壁量計算です。
許容応力度設計でも慣例的な表現として壁倍率を使いますが、実際の計算では 壁倍率1倍=せん断耐力1.96kN/mに直して検討しています。
さて、耐力壁の強さの指標として壁倍率が定められていると前述しましたが、壁倍率が与えられていないものでも耐力壁としての有効耐力をもつものがあります。
門型フレームや方杖フレームなどは耐力壁として耐力上有効に働きますが、耐力壁認定(大臣認定)を取っていない(取れない)ものがほとんどです。
また、狭小壁とも呼んでいる柱脚金物と集成材による扁平柱(ベースセッター(BXカネシン製))なども、告示1100号では仕様規定されない耐力要素となりますね。
つまり、これらフレーム系は壁倍率を有していません。フレーム系の耐力壁は令46条の壁量計算が行えないので、第2項の適用として構造計算を行います。(2項ルート)
「門型フレームを使用する場合は、構造材をオール集成材にしてください」というルールはこの令46条第2項に由来します。
☆木造建築物の関連法規解説シリーズ 次の記事:第46条 構造耐力上必要な軸組等(3)
☆木造建築物の関連法規解説シリーズ 前の記事:第46条 構造耐力上必要な軸組等(1)
用語集タグ一覧
[全て見る] [構造] [木造] [軸組] [ツーバイフォー] [省エネ] [制度]